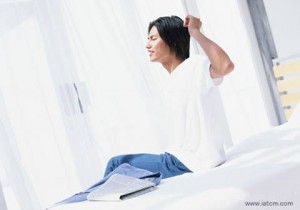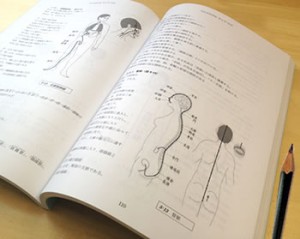骨粗鬆症による骨折や痛みの発生の治療では、虚証と実証の鑑別がまず必要です。
時に、固定観念のように痛みの原因を、「不通則痛」(通らなければ、すなわち痛みが生じる)ととらえて活血剤などを選択する方も少なくありません。
虚労の弁証論治では、気血陰陽を幹とし、五臓の虚証を枝葉と考え、先ず気虚、血虚、陽虚、陰虚などを鑑別して、次に病気の部位を判断します。
治療に当たる際には、十分に虚実の鑑別に心がけて弁証論治を行ってほしいと思います。
骨粗鬆症の治療は非常に難しいですが、痛の原因を治療することが肝要です。
カテゴリー
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2014年5月
- 2014年2月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月