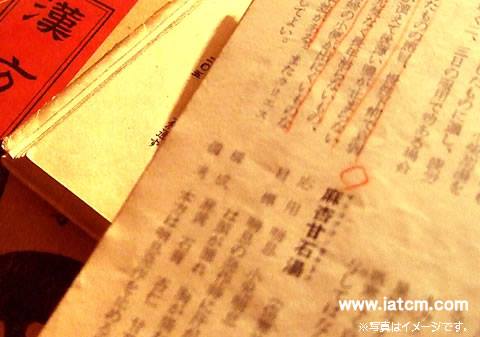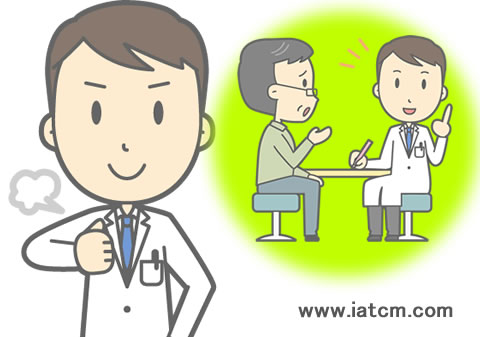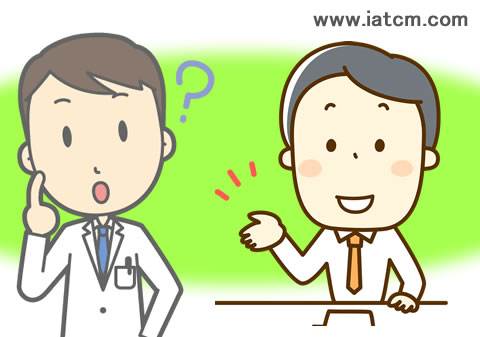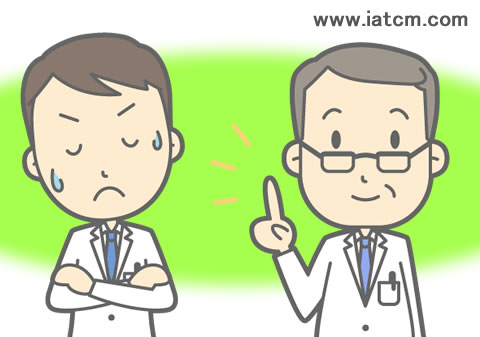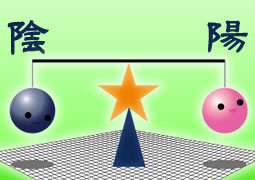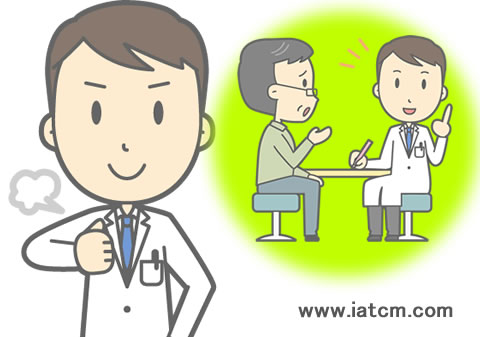
臨床体験の続きをお話しします。
前回お話しした「性」でお悩みの患者さんが、ある日突然大学の寮まで訪ねてきました。
彼はいきなり「董先生! ありがとうございます!薬が効きました!」と僕の手を握って何度も頭を下げて言うのです。
それまでどんな西洋医薬を試してもダメだったのだそうです。
今回薬が効いた事が本当に嬉しそうでした。
結局、その患者さんに「処方箋にあなたの名前があった。だからあなたに続けて診てほしい。」と言われ、仕方なく「では、もう少し同じ薬を続けましょう」と伝えて帰ってもらいましたが、その間中、ルームメイトがみんな必死で笑いをこらえていたのは言うまでもありません。
「中医学をバカにしていた中医学劣等生の董が、『先生』と呼ばれて、中医薬を偉そうに処方しているぞ…」と。
それからしばらくは、「董先生!」とからかわれて、随分ばつの悪い思いをしました。
しかしながら、このことは僕自身も衝撃でした。
中医薬は臨床薬だった… 中医薬はちゃんと出せば本当に効く!
雷に打たれたような「知柏地黄丸」の一件以来、私はガラッと変わりました。
洋の東西を問わず、医療を志す者にとって、「効く」ということは大きな魅力です。
その後、さまざまな中医学の本を読むようになり、今までさぼってきた理論を復習しつつ、中医学の雑誌を読む習慣ができました。
もともと科学的思考好きな私は分析オタクでもあります。
自分のとったメモなどから、最新の中医学の臨床でも、大学1~2年で習う基礎理論の考え方がものすごくよく使われることがわかってきました。
「これ、こんなに大事だったんだ」、というか、「こんなに使うものなんだ」と遅ればせながら気づきました。
それから、「基礎理論・大嫌い」が「基礎理論・命」に180°変わったんです。
たぶん今、中医学や漢方をもっと学ぼうと思われている皆さんの多くが、「中医薬が効いた!」という嬉しい驚き体験がきっかけではないかと思います。
それでせっかく学び始めたのに、そして、早く生薬や処方のことを学びたいのに、まずは基礎理論からで、「あーあ」と思われることもあると思います。
でも実は、理論を理解して活かすことで、本当にいい薬を出せるようになるんです!
そのことを是非忘れずに、基礎理論を味方につけて頑張ってほしいと思います。
漢方の勉強は「国際中医師アカデミー」