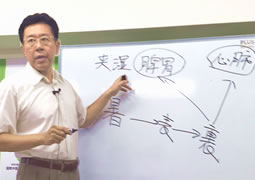中国では、漢方のお医者さんのレベルを、「上工」「中工」「下工」と分けています。
どのような違いがあるのでしょうか?
今日は「下工」についてご紹介します。
中医学では、ダメな漢方屋さんを「下工」といいます。
いろいろな特徴がありますが、まず肝心なところをあげましょう。
■特徴その1: 問診の目的をはっきりと持っていない。
そもそも患者さんに症状を訊く理由は、弁証するため、たとえば気虚なのかどうなのかを判断するために訊くわけです。
そういう見極めを意識せずにただ話を聞くのでは、処方の方針も立てられない下工です。
■特徴その2: 漢方薬の出し方を効能書きに頼り、根拠となる漢方薬の生薬の配合や構成を知らない。
断片的な知識で、朝鮮人参はアンチエイジングにいいと聞きかじったから、老化による症状っぽい患者さんに使ってみようというような処方をする…。
実際はその患者さんの体質が実なのか虚なのか弁証が必要です。
実ならアンチエイジングだからと朝鮮人参を出しても効きません。
■特徴その3: 漢方薬が効いても効かなくてもその理由がはっきりとはわからない。
生薬の効能や特徴を理解せずに、「効かないようならメーカーを変えてみましょう」とか、「漢方はマイルドに効くのに、効果はわかりにくのです」といった説明をするようでは、「下工」と言われても仕方ありません。
漢方を勉強しようという意欲をお持ちの皆さんには「中工」や「上工」を目指していただきたいですね。
次回は「中工」についてご紹介します。