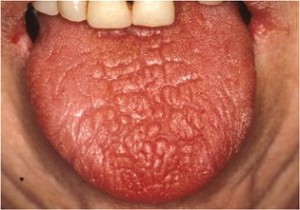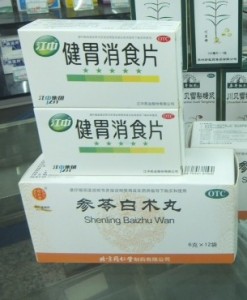9月8日未明、2020年東京オリンピックの開催が決まりました。ブエノスアイレスとの時差は約12時間ありますので、深夜から早朝にかけて開催の決定の瞬間を固唾を飲んで見守った方々は、さぞお疲れだと思います。東京の開催決定に本当におめでとうございます。よくやったなと思い、2020年に東京オリンピックを見るのを楽しみにしております。
中医学では、一日を陰と陽に分けて考えています。太陽が昇るころから太陽が沈むまでを「陽」、太陽が沈んでから、また太陽が昇るまでを「陰」とします。決定の一方が入ったころは早朝の5時頃とあって、この時間帯は、陰が極まりから陽に転化する時間帯です。この時間帯に興奮が続けば陰陽のバランスを崩す恐れがあります。
今日からは生活のリズムを取り戻しましょう。