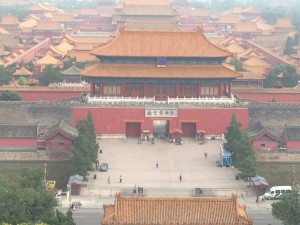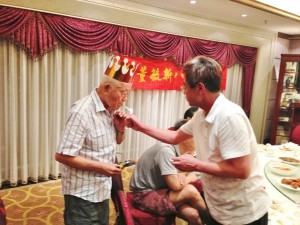私は、スポーツが大好きでスポーツ番組をよく見ます。なかでも私は福原愛さん、松井秀樹さんのファンです。スポーツ番組では選手の表情もよくみられるので、観察する意味でもよく見ています。
時々選手の顔をみていると、唇、歯茎や舌色が紫っぽい方をかなり見ます。紫色や黒ずんだ色は、血流が悪く瘀血の印とする色です。
プロ選手のトレーニング方法についてわかりませんが、瘀血を生じる原因として、外傷、肝鬱気滞、気虚、腎虚などが挙げられます。
腎虚と気虚の原因は、トレーニングの量が多く体の精気を傷耗しすぎる可能性が高いと考えられますので、適度に体の精気を補いながら体力と運動量の調節が必要だと思います。
肝鬱気滞の原因は競争や実績などの不安要素が多く、過度にストレスが高まり、うまく取り除けない可能性が考えられます。
現役時代には、体の不調や異変には気が付かないことが多いのですが、30代後半から、疲労が取れない、白髪が増える、腰の怠さ、同じ運動量でも疲れやすい、胃腸及び月経不順などが段々現れるようになったら、その原因は、精気不足による瘀血が考えられます。
希望ですが、トレーニングの効果をあげるために、栄養学の専門家による管理は勿論ですが、中医学の知識も取り入れて欲しいと思っています。中医学では、体の精気及び瘀血などの意味を深く理解でき、選手の陰陽、五臓、気血、精気などの状態を理解し、適切なアドバイスが行えます。
日本では、中医学の学習を修めた方達は「国際中医師」として活躍しています。