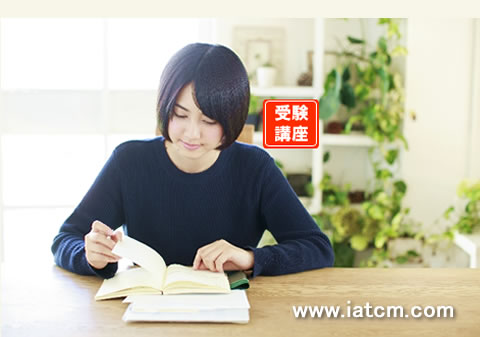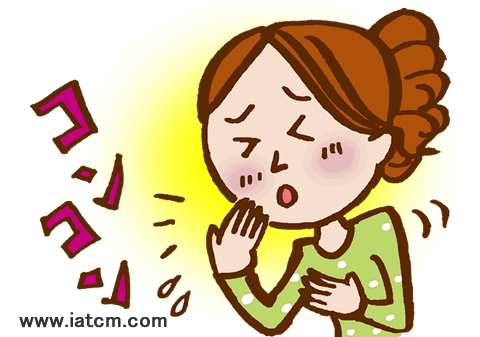「厚着をしても冷える」、「あるいは布団の中で足先がいつも凍ったように冷たくて、寒くて寝られない」、というような冷え性でお悩みの方は、中医学で陽気が非常に弱い状態「陽虚」だと考えられます。
陽虚には主に脾陽虚と腎陽虚がありますが、この二つの治療法は全く違うので注意が必要です。
また、冷え性の方で冷たい汗が出てくる場合がありますが、これは陽気が弱いために津液を留めておく力が弱くなり、津液がもれていると考えられます。
陽虚が一歩進んだ(悪化した)状態ですので、できるだけ早く漢方のプロに相談し、弁証してもらうことをお勧めします。
というのも、冷え性の方は、我流の養生で状態を悪化させてしまうことも多いのです。
たとえば体がなかなか温まらないからと、「生姜(汁)をたくさん摂ろう」といった考えをよく聞きますが、長い間冷え性に悩まされている人は、生姜はやめたほうがいいでしょう。
その理由は、生姜(ショウキョウ)の効能にあります。
生姜の働きには「温陽」はありません。でも「散寒」はできます。
つまり、邪気が入ったときには解表薬(いわゆる風邪薬)として、その邪気を追い出すことができますが、そのときに陽気、気・血・津液も一緒に発散して出してしまうのです。
そのため、生姜を単独で大量に長期間に渡って使うと陽気を消耗し陽虚を発生させてしまいます。
生姜を料理などで普通に食べるレベルであれば問題はありません。
しかし、ほてり、寝汗、眠りが浅い長期間の冷えや、特に女性で生理の後の冷えが強いタイプの方々は、生姜ドリンクなどを摂るのは控えた方がいいでしょう。
効能、効果があると言われるものがいろいろありますが、あなたの体に合うか合わないか、必要かどうかをきちんと見極めていくことが大切です。
漢方の勉強は「国際中医師アカデミー」