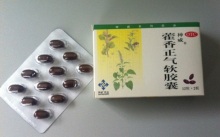体操の男子団体戦の内村選手の判定で、またも誤審がありました。演技の評価が低く判定されたため、チームコーチが抗議した結果判定が覆りました。
今回のオリンピックは、このようなトラブルが多いように感じます。
中医臨床でも、審判のミスと同様なことがあります。あの時、この症状を確認すべきだったとか、何故この問診をしなかったか、などなど、「あっ」と思うことがないとはいえません。
大切なことは、問題点に早く気付き修正することです。これは中医学の腕を上達させるために欠かせない「人格」であると思います。国際中医師アカデミーで多くの問題を練習していただく目的の一つは、自分のミスをどんどんみつけて、更に深く理解し中医学の弁証論治の腕をあげられることです。
自分自身の誤りや不足に気づき、訂正し努力を続けられることが、進歩に繋がる原動力になると考えています。
カテゴリー
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2014年5月
- 2014年2月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月